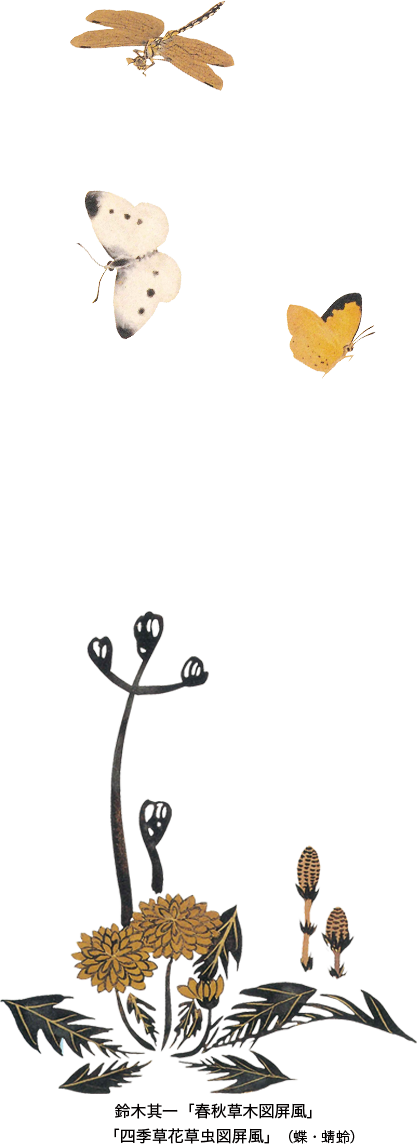古典の日絵巻Picture scroll
「古典の日」からとっておきの情報や
こぼれ話などをお届けします。
古典の日絵巻 第十巻:京の美を担う次世代の作家たち
古典の日絵巻「第十巻:京の美を担う次世代の作家たち」をお届けいたします。
今年度は12回に亘り、それぞれのジャンルで活躍される作家の皆さんから、ものづくりやお仕事にかける想いを綴っていただきます。伝統と先端の間に立って挑戦し、誕生するものとは一体どのようなものでしょうか。作家の皆さんの手によって誕生するまでの知っているようで、知られなかった世界をお話いただきます。
-

3月 江里 朋子 截金作家
-

2月 平井 恭子 木版画摺師
-

1月 羽田 登喜 染色工芸家
-

12月 種田 真紀 絵付師
-

11月 山本 茜 截金ガラス作家
-

10月 八木 隆裕 茶筒職人
-

9月 青山洋子 和菓子職人
-

8月 杉本晃則 塗師・島本恵未 蒔絵師
-

7月 小倉智恵美 竹工芸作家
-

6月 伊東庄五郎 御所人形師
-

5月 諏訪蘇山 陶芸家
-

4月 吉岡更紗 染色家

第1回
吉岡 更紗(よしおか さらさ) 染司よしおか6代目
京都で江戸時代末より200年以上続く染屋「染司よしおか」に生まれる。
アパレルデザイン会社勤務を経て、愛媛県西予市野村町シルク博物館にて染織にまつわる全ての技術を学ぶ。2008年より「染司よしおか」にて自然界に存在する染料を使い制作をおこない、東大寺修二会など古社寺の行事に関わり、復元にも取り組んでいる。2019年六代当主となる。
私は、京都の南、向島という地で、染織工房を営んでいる。紫草(むらさき)の根、蓼藍(たであい)の葉、茜(あかね)の根などすべて天然の染料から色を汲み出し、絹や麻、木綿など天然の生地に色を映す。明治時代にヨーロッパから化学染料が伝わってから、世の中の色は全て化学的な方法で染めるようになっていったが、戦後染屋の仕事を継いだ4代目の祖父の時代から、失われていった植物染料の研究をはじめ、その後5代目を継いだ父は化学染料の仕事を一切やめ、植物染料のみの仕事に戻した。特に、新しいものを求めるエネルギーに溢れていた1980年代のことで、その決断が相当なものであったと思う。
 紅花
紅花
花びらが染料となる。黄色の色素が大半を占めるがわずかに赤い色素が含まれる。
 染和紙
染和紙
2月に入り紅花の「泥」が溜まると和紙を染める作業に入る。
 椿の花とりつけ
椿の花とりつけ
2月23日に選ばれた練行衆の手によって椿の花の形となり、2月27日に椿の枝に花がさされる。その後二月堂内を飾る。
私は2008年から工房に入り、ここ6年ほど毎年年明け1月から2月までは、紅花(べにばな)の作業にいそしんでいる。毎日2kgほどの紅花を水洗いして、黄色の色素を洗い流し、藁灰からとった灰汁で揉むことで紅花に含まれるわずかな赤い色素を汲み出す。その後複雑な工程を経て、その赤い色素を沈殿させる。「泥(でい)」と呼ぶ泥状になった赤い色素は、水で薄めて、刷毛を使い和紙を1枚1枚塗って染めていく。一度では濃い赤にならないので、乾いては塗りを6回ほど繰り返す。
この染和紙は、2月20日頃毎年奈良東大寺にお納めしている。3月1日から2週間東大寺でおこなわれる修二会のためである。法会が執り行われる二月堂の堂内に、その染和紙を使って作られた椿の花が堂内を飾る。この修二会は東大寺大仏が開眼された752年から一度たりとも休むことなく毎年行われる「不退の行法」である。戦時中は物資が不足したこともあり、この椿の花は一般的な折り紙で作られていた時期があったのだが、古の姿に戻すべく、50年ほど前より祖父が、和紙の染めをお引き受けすることとなった。
紅花で染めた赤い和紙60枚をお納めするのだが、1枚の和紙を染めるのにおおよそ1㎏から1.5㎏程の紅花が必要で、最低でも60㎏の紅花と対峙する計算になる。同じ作業を繰り返し、赤60枚白60枚、梔子で染めた黄色の和紙60枚合計180枚の染和紙をお納めした時は、ただただ安堵の一言である。寒い時期の作業になるが、当然ながら体調も気持ちも整えて作業に挑んでいる。1270年続く行にふさわしいように、毎年より美しい赤や黄に染められるように集中するのである。
本年はウィルスの影響もあり、東大寺内は厳粛に厳粛を重ねた形で行を行われた。災害や戦乱にも絶えることなく続けられる行に、色どりを添える仕事を継承できることは染織家として大変ありがたいことである。一年一年の積み重ねが技の伝承となり、更なる美しい色への探求が続いていくのである。