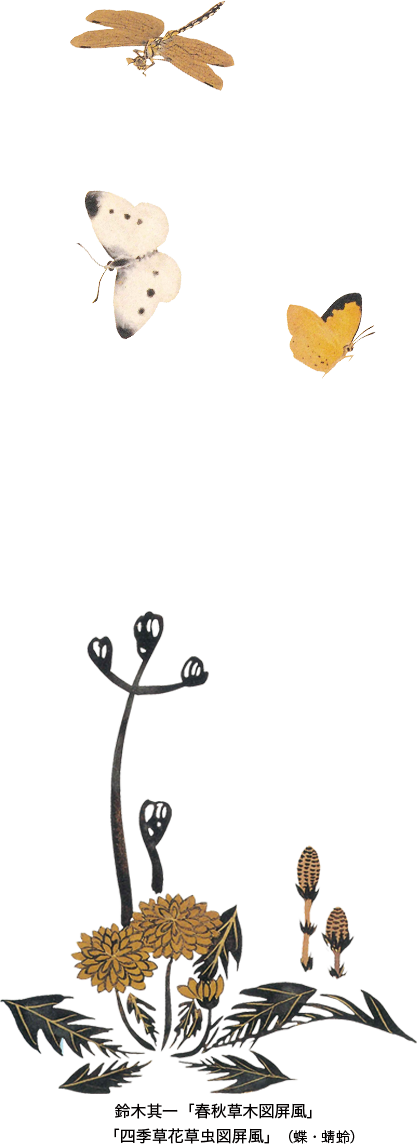フォーラムForum
古典の日フォーラム2025
「古典の日フォーラム2025」の開催について
2026年に「寛永行幸400年」を迎えます。人々のくらしにゆとりが生まれ、京都、大阪、江戸で文化が花開きました。町に立てられた芝居小屋は大にぎわい。画期的にも書物を印刷・出版され流通したのもこの頃です。京都では伝統工芸が栄え、学問や教育の場があちらこちらで開かれ、日本人の教養を高めた文化芸術が発展しました。本フォーラムは江戸時代にスポットを当て、庶民の文化として発達した江戸時代の文化についての講演や文楽をとおして感じ取っていただきます。
また、2022年から実施している国民文化祭との連携を深め、今年の開催地、長崎県対馬市に伝わる命婦の舞を披露していただきます。
1:日 時
令和7年11月1日(土) 13時~16時(開場12時)
2:会 場
ロームシアター京都メインホール(京都市左京区岡崎最勝寺町13)
3:入場料
1,500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください
※チケット販売は、8月1日 10時から開始
4:内容
[第1部]
◆テーマ曲「古典の日燦讃」と「古典の日宣言」
演奏:大谷祥子(箏)藤林由里(ピアノ)饗庭凱山(尺八)
平山美萌(バイオリン)徳安芽里(チェロ)祝丸(太鼓・鳴り物)
朗読:長谷川聖花(第16回古典の日朗読コンテスト【中学・高校生部門】大賞受賞者)
◆第40回 国民文化祭「ながさきピース文化祭2025」との連携
メッセージ 大石賢吾(長崎県知事)
命婦の舞(国選択無形民俗文化財) 命婦の舞保存会
[第2部] 「江戸時代の文化」
◆講演「花開く町人の文化」
澤田瞳子(作家)
◆人形浄瑠璃文楽「『義経千本桜』二段目 知盛幽霊の段」
太 夫 竹本織太夫 三味線 鶴澤清志郎 人 形 吉田簔紫郎 他
◆上演の後のお楽しみ!「アフタートーク 文楽の魅力」
コーディネーター 三宅民夫
司会 三宅民夫(元NHKアナウンサー)
※敬称略
※プログラムは予告なしに変更する場合がございます。
5:出演者プロフィール
◆講演
澤田瞳子(さわだとうこ)/作家
 |
京都府生まれ。同志社大学文学部文化史学専攻卒業、同大学院博士前期課程修了。同大学客員教授。2011年、デビュー作『孤鷹の天』で中山義秀文学賞、『満つる月の如し 仏師・定朝』で新田次郎文学賞、『若冲』で親鸞賞、『掛け入りの寺』で舟橋聖一文学賞、2021年『星落ちて、なお』で第165回直木賞を受賞。『火定』『落花』『しらゆきの果て』など著書多数。近著『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』では、歴史作家ならではの眼で京都を紹介。 |
◆人形浄瑠璃文楽
文楽とは?

「義経千本桜」より「渡海屋銀平実は中納言知盛」 |
人形浄瑠璃文楽は、日本を代表する伝統芸能の一つで、太夫・三味線・人形が一体となった総合芸術です。その成立ちは江戸初期にさかのぼります。太夫と三味線は、お互いの意気を合わせ対等な立場で、緊迫した呼吸を積み重ね義太夫節を組み立てていきます。文楽の人形は、人形一体を三人の人形遣いが操る、世界でも例を見ないもので、微妙な動きはもちろん心情までも表現し、生身の人間以上に訴えかけるものを持っています。 |
『義経千本桜』二段目 知盛幽霊の段
今回、ご披露するのは、「義経千本桜(よしつねせんぼんざくら」の二段目「渡海屋(とかいや)・大物浦(だいもつうら)の段」の中の一場面で、船宿の亭主に身をやつし、宿敵・源義経(みなもとのよしつね)への復讐の機会を狙っている平知盛(たいらのとももり)が、正体を現して、大物浦に義経一行に一矢報おうと出陣する場面です。文楽では、太夫(語り手)と三味線が登場人物のセリフや心情、場面の雰囲気すべてを表現します。知盛が怒りや悲しみに満ちたセリフを語る場面では、声の抑揚や三味線の音が、まるで心の中に入り込んでくるようです。日本の語り芸術の粋ともいえる部分です。人形も白い鎧の知盛は、人間以上の「気迫」や「怒り」を体全体で表現します。みどころは武士の誇りと哀しみを表現する知盛という人物の深み。目を見張るような人形の操作とこれらが一つになった、文楽の魅力がぎゅっと詰まった名場面で、はじめて文楽を観る人でも、言葉がすべてわからなくても、「すごい」「きれい」「迫力ある」と感じられるシーンが連続する段なので、観劇の入り口としてもおすすめです。
◆第40回 国民文化祭「ながさきピース文化祭2025」との連携
命婦の舞(国選択無形民俗文化財)命婦の舞保存会
 |
|
6:チケット購入方法
【販売開始】
令和7年8月1日(金)10時~
【購入方法】
<電話購入>
●ロームシアター京都 チケットカウンター
TEL. 075-746-3201
(窓口・電話とも 10:00~17:00/年中無休 ※臨時休館日等により変更の場合あり)
●京都コンサートホール チケットカウンター
TEL. 075-711-3231
(窓口・電話とも 10:00~17:00/第1・3月曜日 ※休日の場合は翌平日休館)
<Web購入>
●オンラインチケット 24時間購入可
チケット購入はこちらをクリック
・会員登録が必要です。(フレンズ会員は、登録無料です。)
・チケット購入サイトのキーワード検索で「古典の日」と検索してください。